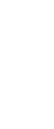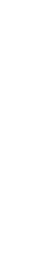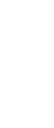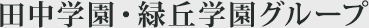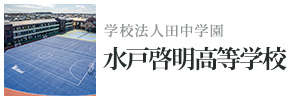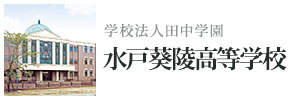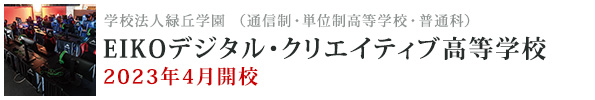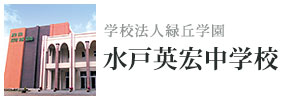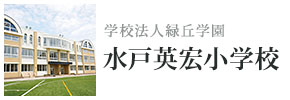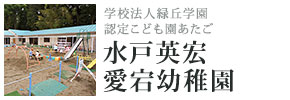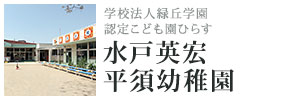お知らせ
2015.5.7花まる先生と「EIKO 5年生の算数」

5年生の算数は,6年間の教科書内容を修了し,小学校総復習・最高水準内容を学んでいます。EIKOオリジナルの「EIKO錬成テキスト」を活用します。
英宏小学校の5・6年の「STAGEⅡ」の学びは,小学校の基礎的・基本的な知識・技能・表現の100%の習得。そして,難関大学・難関学部受験の基礎・基本となる,小学校最高水準内容の習得を目指します。

植えた木の本数と,間の数や長さの関係。(タイプⅠ)
幅に長さがあるものを並べたときの枚数やと,間の数と長さと関係。(タイプⅡ)
これらを求めるのが,「植木算」とよばれる特殊算です。
間の数と本数や枚数にずれが生じていることをもとに考えます。単に公式で「+1」,「-1」と記憶するのではなく,図式化しながら関係をとらえることが大切です。図式化というEIKOメソッドではぐくんだ「自分のツール」を使って考え抜くことによって,高い思考力が育ちます。
教科書にない最高水準の内容を学ぶのは,難易度の高い課題を自分のツールを使って考えぬくことによって,最高水準の思考力を育てるためです。この経験を児童期にすることによって,大学入試時に圧倒的に有利な「思考力」のAdvantageをもつことができます。

今日は,平面上に平面をおくタイプⅡの植木算の学習でした。
「机の上に,5枚のカードを,1列に カードの間も,はしも同じ長さで並べよう。」
という課題で,具体物を用いた作業的な算数的活動を取り入れました。

子どもたちが使ったのは,低学年のときに使用した「算数セット」。高学年の算数でも,最高水準の内容でも,目的がはっきりと意図されている学習では「算数セット」は優れた教具となります。
はじめから,間の長さを考えて取り組む児童や,とりあえず並べてみてから等間隔にする児童。子どもたちは,植木算でもっとも重要な「間の数,長さ」に目をつけているのがわかりました。
「机の横は61cm,カードの幅は5cm,10枚並べると,1つの間の長さは何cm?」
具体的な数値を提示します。
「今日の課題も,間があるので植木算です。」
「今日は,前と違って,カードに幅があります。」
系統を踏まえた授業を展開すると,子どもたちは前の授業との違いや,新たに生まれる不都合に気づきます。
漠然とした流れでなく,教材の本質をとらえ,系統性を意図した授業は子どもたちの思考を整理する手立てとなり,新たに生まれた問題を解決する力,すなわち問題解決力を高めます。

授業のポイントとして,心地よいテンポですすめること。花まる先生の書籍でも紹介されている授業の基本的な技術です。
1つの課題を延々と考えるのではなく,「STAGE型」や「SPIRAL型」などの次の課題をテンポよく与えます。
2つめの課題は「横に10枚1列。たてに6枚並べよう。」です。
ペアで協力しながら,楽しく並べています。
「横は1cmあけて,・・・・」
「縦は?」
「机は39cmあるよ。」
「間は・・・・」
「9÷7!」
子どもたちから,質の高い会話がどんどん聞こえてきました。

5年生は,「EIKO錬成テキスト」を使って最高水準の内容,「高度なことを 早期に 楽しく」学び続けます。ぐんぐん学力を伸ばしている子どもたち。最高水準の学びを本格的に開始して,これからの活躍が楽しみです。
「植木算」は,高校・大学数学で有名な「オイラーの凸型多面体の定理」につながりのある内容です。立体の面と辺,頂点の数は,一定のずれが生じていながら成立しています。
単なる公式の詰め込みをしないのは,今後訪れる問題解決に対して,柔軟な思考力で対応できる人材を大切に育てているからです。