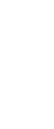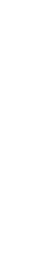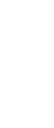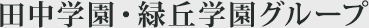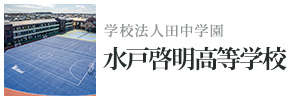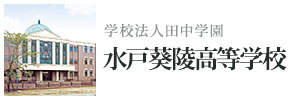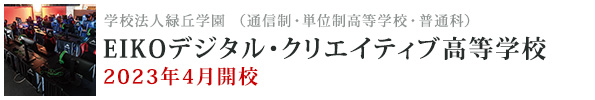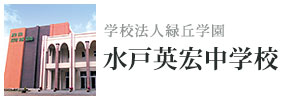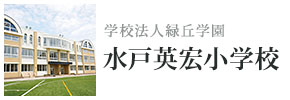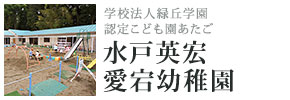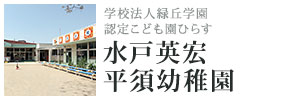お知らせ
2017.2.16避難訓練
本日6校時に校内での火災を想定した避難訓練を実施しました。警報が鳴ると同時に机の下に隠れる児童が・・・地震ではなく火災であるという放送が入るとすぐに防災頭巾をかぶり避難体制をとることができました。

火災であることが分かると同時に口を手やハンカチで押さえて避難をする児童が大半でした。日頃から防災について意識をしながら生活をしてことの表れだと感じる一面でした。

教頭先生は,警報が鳴った時には放送をよく聞くことが大切であると子どもたちに話されていました。

火災・地震・不審者など,様々な警報の種類があります。放送をよく聞くことでどのような避難体制をとるべきなのかを判断する材料になり,そのことが自分の身を守る手段にほかならないということを伝えておられました。

児童による消火活動の様子です。

低学年にとって消火器は重くて扱いにくいものの様でしたが,一生懸命に真剣にとり組んでいました。

高学年の児童は「火事だ!!」と大声でみんなに知らせて消火活動を行いました。
水消火器を上手に使って炎の下方を狙って水をかけていました。
最後に,本日の避難訓練の感想を児童が述べました。幼稚園の時に消火器を使ったことがあったが今回の避難訓練で消火器の使い方を再認識することができて良かったという内容でした。日頃の訓練に真剣に取り組むことで火災が起こった時にどのような行動を取るべきなのかを考えることができる機会になりました。

児童たちと同様に教職員も緊急時の心構えを改めて確認することができる避難訓練であったと思います。